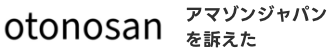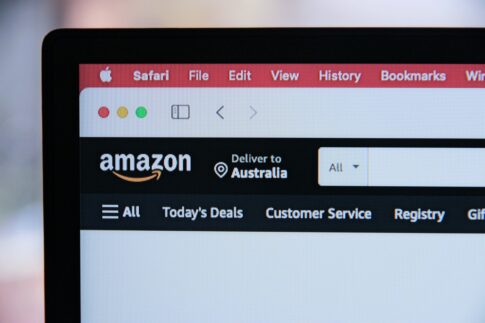- Amazonは2022年10月7日、「ストア上の説明と違う」と商品をすり替えて返品した購入者に全額返金し、商品がすり替えられたと主張する原告に対し、「当ストアでは、購入者様の返品時のコメントに従い返金を行っており、真偽の確認は行っておりません」と無責任な回答を行い、原告の返金要求を拒否した(訴状34頁(2)ア)。
- 本件ストアでは、商品の販売を倉庫での保管から発送までをAmazonに一括して依頼する場合、保管料や配送料算定のため、出品者に、梱包状態(パッケージ寸法)のサイズや重量の登録を義務付けている(甲188)。自己申告制ではなく、Amazonが倉庫での受領時にも計測を行っており、出品者が集うセラーフォーラムでは、Amazonによってサイズが大きく見積もられており、再計測を求めたが納得できないという投稿も寄せられている(甲189)。
- すり替えられた商品は、後に原告がフリマサイトで転売されていることを発見したが、原告が販売した商品【資料1】とすり替えられた商品【資料2】は、デザイン、色、素材すべてにおいて全く異なるものであり、納品時の外装パッケージが透明であることから、中身が異なることは容易に判断できるものであった。また、すり替えられた商品は、原告が納品時に申告したもの(2.5kg)よりもはるかに軽量であった(1.6kg)。
【資料1】

【資料2】

重ければそれだけコストと負担となるため、原告が実際より重く申告する理由はなく、Amazonに対し、上記事実以外にもすり替え詐欺を証明する十分な証拠をAmazonに提出したが(甲25の1)、Amazonは調査の協力を拒否した。 Amazonはプラットフォーマーとして販売の場を提供するだけでなく、自ら販売も行っており、原告が被害を受けたようなすり替え詐欺に対処する目的で、倉庫からの発送時に発送商品に間違いがないか梱包状態の記録を残していることは明らかであり、またAmazon倉庫に預けている原告商品を発送したのはAmazonであることから、商品を間違えることなく発送した証拠を示すことができるのはAmazonのみであり、原告では不可能である。Amazon倉庫から発送された商品と、すり替え詐欺を行った悪質購入者が被告に返品してきた商品が同じものであったか確認すべきところ、Amazonは意図的にこれを行わなかった。
- 当該商品は日本国内では販売されていない珍しい商品であり、原告がどこかで転売されていないか調査した結果、たまたま悪質購入者がすり替えた商品を原告ストアのロゴを使用してメルカリで販売しており、同時に本件ストアに返品された商品の色違いも販売していたため、原告はすり替え詐欺であることを突き止めることができた。
- 原告がすり替え詐欺の明らかな証拠を提出したうえで再度交渉を行い、ようやくAmazonは商品代金の返金に応じたが、原告が販売した3万98000円ではなく、補填処理を実施するという名目の、Amazonが一方的に商品相応額とする2万9100円のみであった。当該商品は原告以外には販売しておらず、この金額が具体的に何を元に算出されたのか証憑の提示がなく、正当な金額でないことを示す根拠がないことは正常な商習慣に照らし、不当に不利益を与える優越的地位の濫用であり、その根拠を求めるにはAmazonに訴え続けねばならず、費用対効果を考慮しなければならない問題となっている(甲190)。
- なお、Amazonによる補填処理については、2023年11月2日にも、Amazonが倉庫内で保管していた2980円の原告商品を破損し、商品相応額とする1929円が返金されたが(原告第12準備書面39頁ウ)、これについては本書面(3)において補足説明を行う。
- すり替えられた商品がすべてフリマサイトで転売されるとは限らない。Amazonは、自らが受けた被害については悪質購入者を排除するなど対策を講じることができるが、出品者販売については、Amazonが保管し、発送し、返品を受け付けているにもかかわらず、すり替え詐欺を見抜く協力を拒否し、その真偽の確認は一切行わないなどと責任を放棄し、放棄したからといって悪質購入者の情報を開示することもない。そのため、出品者は明らかな証拠がなければ、すり替え詐欺などには泣き寝入りしかない状況である。
- すり替え詐欺が犯罪(刑法246条1項)であるにもかかわらず、Amazonが見過ごすのをよしとするのは、自らはすり替えられた商品か確証を得ることが容易である優越的立場にあるのに対し、出品者はすり替え詐欺であるという確固たる証拠を自らが示さなければ商品、代金、手数料のすべてを出品者側が負担しなければならない出品者の不利益が、調査を行うコストと想定される結果においてAmazonに都合のよい利益になっている事実からであり、独占禁止法(以下、「独禁法」という。)が指定する「その他取引の相手方に不利益となるように取引を実施すること」(独禁法2条9項5号ハ)にあたり、出品者は制限された情報のみで確固たる証拠を探さなければならず、本件ストアにおいて正当に営業活動を行う権利が侵害されている。
また、実店舗での万引き犯罪による取引被害と異なり、インターネット通販という証拠が入手しやすい商取引にもかかわらず犯罪を取り締まらないことは、コストが消費者に転嫁される結果となり、Amazonがすり替え詐欺だと訴える出品者の協力要請に応じないことは、消費者にとって不利益となることを付言する。
PDF:ページ1-6を参照